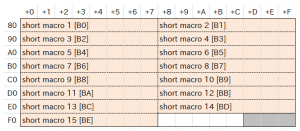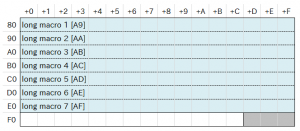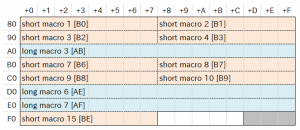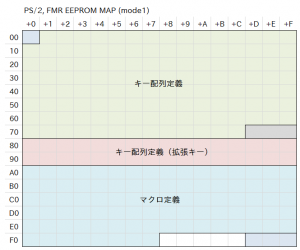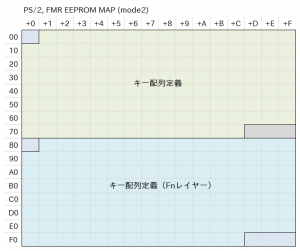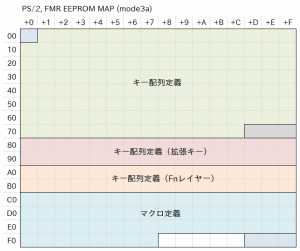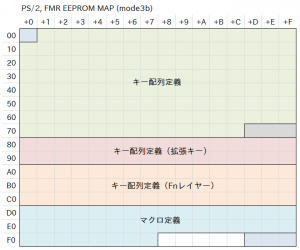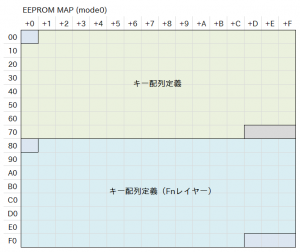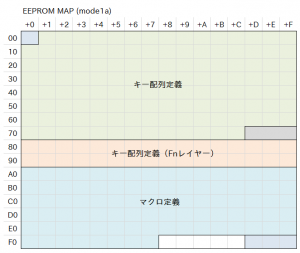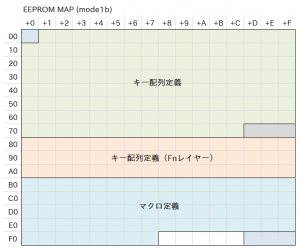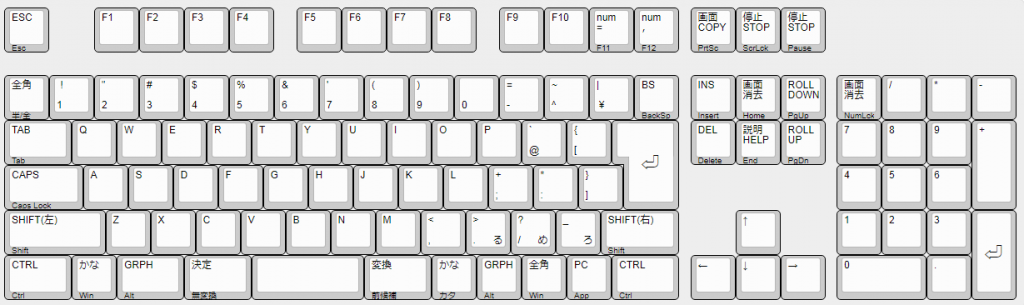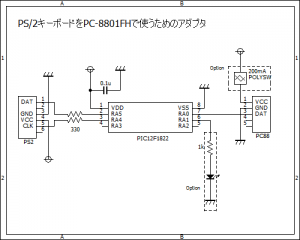各アダプタごとの設定ビット説明
設定ファイルに記述する際は、値の頭に “$” をつけると2進数での記述が可能です
(例: “FF, $01100111” と “FF, 67” は同じ)
未使用のビットは0でも1でもどちらでも構いません
なおファームウェア更新直後はすべてのビットが “1” に初期化されます
X68000
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 (0xFF) | DSC | MODE | MODE | - | - | SCLK | SYSC | KITT |
| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
設定1 (0xFF)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 7 | DSC | スクリーンセーバー殺しの機能を有効化するか 1=無効 (初期設定) 0=有効 |
| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 (初期設定) 01=mode1a 00=mode1b |
| 2 | SCLK | Scroll Lock LEDの状態にあわせてレイヤーの切り替えを行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (Scroll Lock LED点灯中は常に Layer1 を選択する) |
| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |
| 0 | KITT | 1=無効 (初期設定) 0=有効 |
設定2 (0x7D)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |
PC-9801 Series
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | WIN | KGEN | MKBR | SYSC | - |
| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
設定1 (0xFF)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 01=mode1a 00=mode1b |
| 4 | WIN | Windowsキーを有効にするか (※ WInキーを有効にする場合は、必ずKGENも0に設定すること) 1=無効 (初期設定) 0=有効 |
| 3 | KGEN | キーボードの世代を指定 1=LEDなし、CAPSとかなは機械式のロッキング (初期設定) 0=LEDあり、CAPSとかなはファームウェアによるソフトウェアロッキング ※ この設定は次のように読み替えることも出来ます |
| 2 | MKBR | CAPSとかなのロッキング対応を行うか 1=行う (初期設定) 0=行わない |
| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |
設定2 (0x7D)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |
ADB
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | POW | - | MKBR | SYSC | - |
| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
設定1 (0xFF)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode0 01=mode1a 00=mode1b |
| 4 | POW | NeXT ADB キーボード使用時、Powerキーを有効にするか (※ NeXT ADB キーボード以外のキーボードは常に1にすること) 1=無効 0=有効 |
| 2 | MKBR | caps lockのロッキング対応を行うか 1=行う 0=行わない |
| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない 0=行う (2秒の長押しが必要) |
設定2 (0x7D)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |
FMR/FM TOWNS/OASYS
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 (0xFF) | - | MODE | MODE | - | - | - | SYSC | - |
| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
設定1 (0xFF)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode1 10=mode2 01=mode3a 00=mode3b |
| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない 0=行う (2秒の長押しが必要) |
設定2 (0x7D)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |
PS/2
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 (0xFF) | DSC | MODE | MODE | - | FMEX | - | SYSC | - |
| 設定2 (0x7D) | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
設定1 (0xFF)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 7 | DSC | スクリーンセーバー殺しの機能を有効にするか 1=無効 (初期設定) 0=有効 |
| 6-5 | MODE | 動作モード指定 11=mode1 (初期設定) 10=mode2 01=mode3a 00=mode3b |
| 3 | FMEX | 富士通キーボードの拡張コマンドを送信するか 1=送信しない (初期設定) 0=送信する |
| 1 | SYSC | システムコントロールキー操作時、誤操作防止を行うか 1=行わない (初期設定) 0=行う (2秒の長押しが必要) |
設定2 (0x7D)
| BIT | NAME | 説明 |
|---|---|---|
| 1-0 | LED | LEDの点灯モードを指定 00=1秒おきに点滅&キー操作のタイミングで反転 (初期設定) 01=キーを押した瞬間に短く点灯 10=キーを押している間中、点灯 11=常時消灯 |